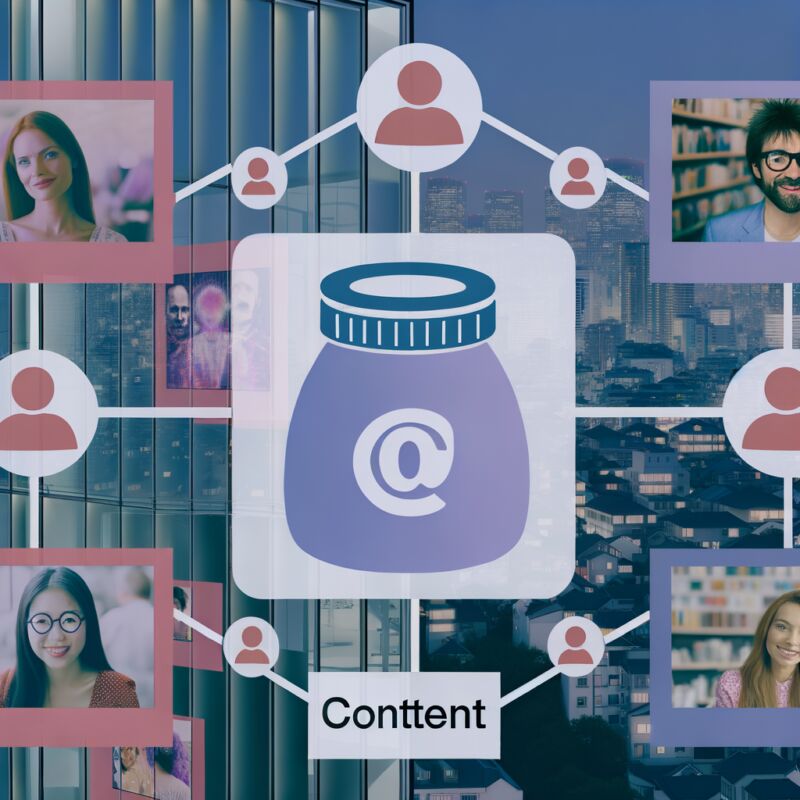「コンテンツ不足で悩んでるけど、何から手を付ければ…?」そんなあなたへ。コンテンツ不足は、Webサイトの成長を阻害する大きな要因。でも大丈夫!この記事では、コンテンツ不足の原因を徹底分析し、すぐに実践できる解決策を具体的にご紹介します。質の高いコンテンツを増やし、ユーザーを惹きつけるWebサイトへと変身させましょう!
コンテンツ不足とは?,不足の原因を深掘り
コンテンツ不足、ありますよね!私もデジタルマーケティングの現場で、何度もこの問題に直面してきました。そもそもコンテンツ不足って、一体何を指すんでしょうか?単純にコンテンツの量が足りないだけではなく、ターゲットとする顧客層に響く情報が不足している状態も含まれます。
例えば、ウェブサイトにアクセスは多いのに、コンバージョン率が低い場合。これは、コンテンツが顧客のニーズを捉えきれていない、つまり「コンテンツ不足」の状態と言えるでしょう。コンテンツの質、量、そして適切さ、これらすべてが揃って初めて、効果的なコンテンツマーケティングが実現するんです。では、その原因を深掘りしてみましょうか。
コンテンツ不足を引き起こす根本原因
コンテンツ不足の原因は様々ですが、よくあるのは戦略の欠如です。
- ペルソナ設定の甘さ: 誰に向けてコンテンツを作るのかが曖昧だと、当然、顧客に響くコンテンツは生まれません。
- キーワード調査の不足: 顧客がどんなキーワードで検索しているのかを把握していなければ、見つけてもらうことすらできませんよね。
- コンテンツ企画のマンネリ化: いつも同じような内容ばかりでは、顧客は飽きてしまいます。新しい視点や切り口を見つける努力が必要です。
コンテンツ不足を放置するリスクとは?
コンテンツ不足を放置すると、ビジネスに様々な悪影響を及ぼします。
- SEO評価の低下: コンテンツが少ないと、検索エンジンからの評価が下がり、ウェブサイトへのアクセスが減ってしまいます。
- 顧客満足度の低下: 必要な情報が見つからないウェブサイトは、顧客にとって不便でしかありません。
- 競合他社との差の拡大: 競合他社が充実したコンテンツを提供している場合、顧客はそちらに流れてしまうでしょう。
コンテンツ不足を感じた時の最初のステップ
まずは、現状のコンテンツを徹底的に分析しましょう。Google Analyticsなどのツールを使って、どのコンテンツが読まれているのか、どのコンテンツが読まれていないのかを把握します。そして、読まれていないコンテンツの原因を特定し、改善策を検討しましょう。
コンテンツ不足を解消するための心得
コンテンツ不足の解消は、一朝一夕にはできません。地道な努力が必要です。
- 長期的な視点を持つ: 短期的な成果を求めるのではなく、長期的な視点でコンテンツを充実させていくことが大切です。
- 顧客の視点に立つ: 常に顧客が何を求めているのかを考え、顧客のニーズに応えるコンテンツを作成しましょう。
- 継続的な改善を行う: コンテンツを公開した後も、効果測定を行い、改善を繰り返していくことが重要です。
コンテンツ不足 解決
コンテンツ不足を解決したい!切実な願いですよね。私も過去に、あるプロジェクトでコンテンツが全然足りなくて、本当に頭を抱えた経験があります。ウェブサイトのリニューアルを控えていたんですが、新しいデザインに合わせたコンテンツが全く準備できていなかったんです。
その時は、本当に焦りましたね。徹夜続きでコンテンツを量産しましたが、質は二の次。結果、リニューアル後のアクセス数は伸び悩み、コンバージョン率も期待したほど上がりませんでした。「量より質」って、本当にその通りだと痛感しましたよ。
量を増やすだけではダメ?コンテンツの質を意識する
コンテンツ不足を解消するためには、もちろん量を増やすことも大切ですが、それ以上に質が重要です。
- ターゲット層のニーズを理解する: 誰に何を伝えたいのかを明確にしましょう。
- 独自の視点や価値を提供する: 他のウェブサイトにはない情報や、あなたならではの意見を発信しましょう。
- SEO対策を施す: 検索エンジンに評価されるように、適切なキーワードを使用しましょう。
- 読みやすい文章を心がける: 専門用語を避け、分かりやすい言葉で説明しましょう。
AIを活用したコンテンツ作成の可能性
最近では、AIを活用してコンテンツを自動生成するツールも登場しています。例えば、OpenAIのGPT-3などの大規模言語モデルは、人間が書いたような自然な文章を生成することができます。
AIに記事のテーマやキーワードを入力するだけで、あっという間に記事の草稿を作成してくれるんです。もちろん、AIが生成した文章をそのまま使うのではなく、人間の目で確認し、修正を加える必要があります。でも、コンテンツ作成の効率を大幅に向上させることができるのは間違いありません。
コンテンツの再利用で効率アップ
過去に作成したコンテンツを再利用することも、コンテンツ不足を解消する有効な手段です。例えば、過去に書いたブログ記事を、動画やインフォグラフィックに作り変えることができます。
成功事例から学ぶコンテンツ戦略
コンテンツマーケティングで成功している企業の事例を参考にすることも、コンテンツ不足を解決するためのヒントになります。例えば、Red Bullは、エクストリームスポーツに関する高品質な動画コンテンツを配信することで、ブランドイメージを高め、多くのファンを獲得しています。
解決の糸口:コンテンツカニバリゼーションの回避
コンテンツカニバリゼーションとは、ウェブサイト内で類似したキーワードやテーマのコンテンツが複数存在し、互いに順位を奪い合ってしまう現象のことです。これを避けるためには、キーワードの整理やコンテンツの統合など、戦略的な対策が必要になります。
コンテンツ不足解消のための継続的な努力
コンテンツ不足の解消は、一度解決すれば終わりではありません。常に新しい情報を取り入れ、コンテンツを更新し続ける必要があります。そして、常に顧客の視点に立ち、顧客のニーズに応えるコンテンツを提供し続けることが、成功への鍵となるでしょう。私も、常にアンテナを張り、新しい情報や技術を学びながら、コンテンツマーケティングに取り組んでいきたいと思っています。一緒に頑張りましょうね!

放置のリスク
コンテンツ不足、本当に頭を悩ませますよね!私もAI業界に身を置く一人として、痛いほど分かります。放置しておくと、せっかくのウェブサイトやSNSの魅力が半減。訪問者は必要な情報を見つけられず、すぐに離れていってしまうんです。これは、ブランドイメージの低下にも繋がりかねません。コンテンツがない状態が続くと、検索エンジンのランキングも下がり、さらにアクセスが減るという悪循環に…。
以前、私が担当していたプロジェクトで、まさにこの「放置」をしてしまった苦い経験があります。最初はコンテンツ作成に意欲満々だったのですが、日々の業務に追われ、更新が滞ってしまったんです。結果、ウェブサイトへのアクセス数は激減。クライアントからの信頼も揺らぎかけ、本当に冷や汗ものでした。この経験から、コンテンツ戦略の重要性を改めて痛感しました。皆さんは、同じような失敗をしていませんか?
コンテンツ不足が招く機会損失
コンテンツ不足は、単に情報がないというだけでなく、ビジネスにおける大きな機会損失を招きます。ユーザーが求める情報を提供できないということは、潜在顧客を逃しているのと同じこと。競合他社が充実したコンテンツを提供していれば、ユーザーはそちらに流れてしまうでしょう。
顧客とのエンゲージメント低下
コンテンツ不足は、顧客とのエンゲージメントを低下させます。定期的な情報発信は、顧客との信頼関係を築き、ロイヤリティを高める上で非常に重要です。コンテンツがない状態では、顧客はあなたのブランドを忘れ、競合他社へと乗り換えてしまう可能性があります。
SEO対策の遅れ
SEO(検索エンジン最適化)は、ウェブサイトへのトラフィックを増やすために不可欠な要素です。しかし、コンテンツが不足していると、検索エンジンからの評価が下がり、上位表示されにくくなります。これは、ウェブサイトへのアクセス数を減らし、ビジネスチャンスを逃すことに繋がります。
コンテンツ不足に陥らないための対策
では、コンテンツ不足に陥らないためには、具体的にどのような対策を講じれば良いのでしょうか?まずは、コンテンツ作成の優先順位を上げることが大切です。日々の業務に追われる中でも、定期的なコンテンツ作成の時間を確保するようにしましょう。
コンテンツ作成の計画を立てる
コンテンツ作成の計画を立てることで、何を書くべきか迷う時間を減らし、効率的にコンテンツを作成することができます。キーワード調査を行い、ターゲット層が求めている情報を把握し、それに基づいたコンテンツを作成するようにしましょう。
AIツールを活用する
コンテンツ作成を効率化するために、AIツールを活用することも有効です。例えば、ChatGPTなどのAIライティングツールを使えば、アイデア出しや文章の作成をサポートしてくれます。ただし、AIが生成した文章は、必ず人間がチェックし、修正するようにしましょう。私も最近、AIツールを積極的に活用しているんですが、本当に助けられています!皆さんも試してみてはいかがでしょうか?
コンテンツの質向上策
コンテンツの質向上、これはもう永遠のテーマですよね。質の低いコンテンツは、時間と労力の無駄遣い。ユーザーはすぐに離脱し、検索エンジンの評価も下がり、良いことなしなんです。では、どうすればコンテンツの質を向上させることができるのでしょうか?
私が大切にしているのは、徹底的なユーザー視点。ユーザーが本当に求めている情報は何か、どんな言葉で伝えれば分かりやすいのか、常に考え抜くようにしています。また、情報の正確性も非常に重要。嘘や不確かな情報を提供してしまうと、信頼を失い、ブランドイメージを大きく損なう可能性があります。
質が低いコンテンツの弊害
質が低いコンテンツは、ウェブサイトの信頼性を損ない、ビジネスに悪影響を及ぼします。ユーザーは質の低いコンテンツを嫌い、すぐに他のウェブサイトへと移動してしまうでしょう。これは、ウェブサイトの直帰率を高め、SEO対策にも悪影響を及ぼします。
ウェブサイトの信頼性低下
質の低いコンテンツは、ウェブサイト全体の信頼性を低下させます。誤字脱字が多かったり、情報が古かったりすると、ユーザーは「このウェブサイトは信頼できない」と感じ、他のウェブサイトへと移動してしまうでしょう。
SEO評価の低下
検索エンジンは、コンテンツの質を非常に重視します。質の低いコンテンツは、検索エンジンからの評価が下がり、上位表示されにくくなります。これは、ウェブサイトへのアクセス数を減らし、ビジネスチャンスを逃すことに繋がります。
コンテンツの質を高めるための具体的な方法
コンテンツの質を高めるためには、いくつかの具体的な方法があります。まずは、ターゲット層を明確にすること。誰に向けてコンテンツを発信するのかを明確にすることで、コンテンツの内容や表現方法を最適化することができます。
読者のニーズを理解する
読者のニーズを理解することは、質の高いコンテンツを作成するために非常に重要です。キーワード調査やアンケート調査などを通じて、読者が求めている情報を把握し、それに基づいたコンテンツを作成するようにしましょう。
情報の正確性を確認する
コンテンツを作成する際には、情報の正確性を必ず確認するようにしましょう。信頼できる情報源を参考にし、最新の情報を提供するように心がけましょう。また、誤字脱字がないか、文法的に正しいかなど、校正作業も丁寧に行うようにしましょう。最近、私も情報の裏取りを徹底するようにしています。皆さんはどうですか?
量産体制の構築
コンテンツ不足の解決、本当に頭を悩ませますよね!特に、質の高いコンテンツを継続的に提供していくための量産体制の構築は、多くの企業にとって大きな課題です。私も過去に、あるプロジェクトでコンテンツの量産体制を構築しようとしたのですが、うまくいかず大失敗してしまった経験があります。
最初は、勢いよくコンテンツを作成していたものの、徐々にネタ切れになり、質の低下も目立つようになってきたんです。チーム全体が疲弊し、モチベーションも下がってしまいました。あの時の焦燥感は今でも忘れられません。結局、計画は頓挫し、大幅な軌道修正を余儀なくされました。
コンテンツ量産体制構築の落とし穴
あの時の失敗から学んだことは、コンテンツ量産体制の構築は、単にコンテンツを増やすことだけを目的とするのではなく、持続可能な仕組みを作ることが重要だということです。コンテンツの質を維持しながら、効率的に量産できる体制を構築するためには、しっかりとした計画と戦略が不可欠です。
計画的なコンテンツ戦略の重要性
まず、最初にやるべきことは、明確なコンテンツ戦略を立てることです。ターゲット層を明確にし、彼らが求める情報を的確に把握しましょう。そして、どのようなコンテンツを、どれくらいの頻度で提供していくのか、具体的な計画を立てることが重要です。闇雲にコンテンツを作成するのではなく、戦略的にコンテンツを量産していく必要があるんです。
チームの役割分担と効率化
次に、チームの役割分担を明確にしましょう。誰が企画を担当し、誰が執筆、編集、公開を担当するのか、それぞれの役割を明確にすることで、スムーズな連携が可能になります。また、コンテンツ作成プロセスを効率化するために、ツールやテンプレートなどを活用することも有効です。例えば、コンテンツ作成支援ツールを使えば、アイデア出しから構成作成、校正まで、一連の作業を効率的に行うことができます。
AIツールを活用したコンテンツ量産
最近では、AIツールを活用してコンテンツを量産する方法も注目されていますよね。AIツールを使えば、短時間で大量のコンテンツを作成することが可能です。もちろん、AIが生成したコンテンツをそのまま公開するのではなく、人間の目でチェックし、修正を加える必要がありますが、コンテンツ作成の効率化には大きく貢献してくれるはずです。
AIコンテンツ生成ツールの種類
AIコンテンツ生成ツールには、様々な種類があります。例えば、特定のキーワードを入力するだけで、記事のタイトルや見出しを自動生成してくれるツールや、文章の構成や流れを提案してくれるツールなどがあります。また、既存の記事をリライトして、新しいコンテンツを作成してくれるツールもあります。これらのツールを上手に活用することで、コンテンツ作成にかかる時間や労力を大幅に削減することができます。
AIと人間の協働によるコンテンツ作成
AIツールはあくまでツールであり、最終的な判断は人間が行う必要があります。AIが生成したコンテンツを鵜呑みにするのではなく、必ず人間の目でチェックし、修正を加えるようにしましょう。AIと人間が協働することで、質の高いコンテンツを効率的に量産することが可能になります。
再利用アイデア
コンテンツ不足を解消するための秘策、それは既存コンテンツの再利用です!私も以前、あるプロジェクトでコンテンツ不足に悩まされていた時に、過去に作成したコンテンツを再利用することで、見事に乗り切ることができた経験があります。
最初は、過去のコンテンツを再利用することに抵抗があったのですが、思い切って試してみたところ、意外なほど効果があったんです。コンテンツを再利用することで、新たなコンテンツを作成する手間を省くことができ、結果的にコンテンツの量を大幅に増やすことができました。
コンテンツ再利用のメリットと注意点
コンテンツ再利用のメリットは、時間と労力を節約できるだけでなく、過去のコンテンツを有効活用できることです。しかし、ただ単にコンテンツを再利用するだけでは、効果は期待できません。再利用する際には、ターゲット層や目的に合わせて、内容を適切に修正したり、新しい情報を追加したりする必要があります。
コンテンツ再利用の具体的な方法
コンテンツを再利用する方法は様々です。例えば、過去に書いたブログ記事を、動画やインフォグラフィックに変換したり、複数のブログ記事をまとめて、電子書籍を作成したりすることができます。また、過去のセミナー資料を、ブログ記事やプレゼンテーション資料に再利用することも可能です。
リパーパス戦略で効果を最大化
コンテンツを再利用する際には、リパーパス戦略を意識することが重要です。リパーパス戦略とは、一つのコンテンツを複数の形式に変換し、様々なチャネルで配信することで、より多くのユーザーにリーチする戦略のことです。例えば、ブログ記事を動画、ポッドキャスト、インフォグラフィックなどに変換し、それぞれのチャネルで配信することで、より多くのユーザーにアプローチすることができます。
再利用アイデアの宝庫:眠れる資産の発掘
過去のコンテンツは、再利用アイデアの宝庫です。眠っているコンテンツを掘り起こし、新たな価値を生み出すことで、コンテンツ不足を解消することができます。過去のコンテンツを振り返り、どのようなコンテンツが再利用できるのか、検討してみましょう。
ウェビナーやイベント資料の再利用
ウェビナーやイベントで使った資料は、貴重なコンテンツの宝庫です。これらの資料をブログ記事やインフォグラフィックに再構成することで、新たなコンテンツを生み出すことができます。また、ウェビナーの録画を編集して、短い動画コンテンツとして配信することも可能です。
お客様の声や事例紹介の活用
お客様の声や事例紹介は、非常に説得力のあるコンテンツです。これらのコンテンツをウェブサイトやブログ、ソーシャルメディアで積極的に活用しましょう。お客様の声を集めて、FAQを作成したり、成功事例をまとめた資料を作成したりすることも有効です。
AIツール活用術
AIツール、本当に便利になりましたよね!私も最近、AIツールを積極的に活用してコンテンツ作成に取り組んでいるのですが、その効果に驚いています。特に、コンテンツのアイデア出しや、文章の校正作業など、これまで時間がかかっていた作業が、AIツールを使うことで大幅に効率化されました。
AIツール導入でコンテンツ作成の効率化
AIツールを導入することで、コンテンツ作成のプロセス全体を効率化することができます。例えば、AIツールを使ってキーワード調査を行ったり、競合サイトの分析を行ったりすることで、より効果的なコンテンツ戦略を立てることができます。また、AIツールを使って文章の構成を提案してもらったり、文法やスペルチェックを行ったりすることで、質の高いコンテンツをより短時間で作成することができます。
編集作業を効率化するAI校正ツール
AI校正ツールは、文章の誤字脱字や文法ミスを自動で検出してくれるだけでなく、より自然で読みやすい文章に修正するための提案もしてくれます。これにより、編集作業にかかる時間と労力を大幅に削減することができます。また、AI校正ツールは、文章のスタイルやトーンを調整する機能も備えているため、ターゲット層に合わせた文章を作成することができます。
SEO対策を支援するAIツール
SEO対策は、コンテンツマーケティングにおいて非常に重要な要素です。AIツールは、SEO対策を支援する様々な機能を提供しています。例えば、キーワードの選定や、競合サイトの分析、コンテンツの最適化など、SEO対策に必要な作業を効率的に行うことができます。また、AIツールは、最新のSEOトレンドを常に学習しているため、常に最適なSEO対策を行うことができます。
AIツール活用の注意点と今後の展望
AIツールは非常に便利なツールですが、万能ではありません。AIツールはあくまでツールであり、最終的な判断は人間が行う必要があります。AIツールが生成したコンテンツを鵜呑みにするのではなく、必ず人間の目でチェックし、修正を加えるようにしましょう。
AIに丸投げしない:人間の目と創造性が重要
AIツールは、コンテンツ作成の効率化に大きく貢献してくれますが、人間の創造性や感性を代替することはできません。AIツールを使ってコンテンツを作成する際には、常に人間の目と創造性を大切にしましょう。AIツールを上手に活用しながら、オリジナリティ溢れるコンテンツを作成していくことが重要です。
AI進化でコンテンツ制作はどう変わる?
AI技術は日々進化しており、コンテンツ制作におけるAIの役割は今後ますます大きくなっていくと考えられます。将来的には、AIがコンテンツの企画から作成、配信まで、一連の作業を自動で行うようになるかもしれません。しかし、その場合でも、人間の創造性や感性が重要であることに変わりはありません。AIと人間が協働することで、より質の高いコンテンツを効率的に量産できる時代が来るかもしれません。
成功事例紹介
コンテンツ不足の解決って、本当に頭を悩ませますよね!私自身、AIを活用したコンテンツマーケティングの仕事をしている中で、何度も壁にぶつかってきました。特に記憶に残っているのは、ある中小企業様のウェブサイトリニューアルプロジェクトです。当初、SEO対策もバッチリ!と思っていたのですが、公開後、全くと言っていいほどアクセスが増えなかったんです。
原因を調査した結果、コンテンツが圧倒的に不足していることに気づきました。キーワードはきちんと盛り込んでいるものの、内容が薄っぺらで、ユーザーの疑問に答える情報がほとんどなかったんです。まさに「宝の持ち腐れ」状態…。あの時の焦燥感は忘れられません!
成功への道のり: コンテンツ再構築とペルソナ設定
まず最初に取り組んだのは、既存コンテンツの徹底的な見直しです。キーワード調査をやり直し、ユーザーが本当に求めている情報を洗い出しました。そして、ペルソナを明確に設定することで、ターゲット層に響くコンテンツの方向性を見定めました。ペルソナ設定、本当に重要ですよ!
具体的なコンテンツ戦略
ペルソナに基づき、ブログ記事、FAQ、事例紹介、動画など、様々な形式のコンテンツを制作しました。特に力を入れたのは、お客様の「生の声」を反映した事例紹介です。成功事例だけでなく、失敗事例も包み隠さず公開することで、ユーザーの共感を呼び、信頼感を高めることができました。
SEOに強いコンテンツ作成術
コンテンツを制作する際には、SEO対策も怠りませんでした。キーワードの適切な配置はもちろん、内部リンクを効果的に活用することで、ウェブサイト全体の評価を高めることができました。また、構造化マークアップを施し、検索エンジンにコンテンツの内容を正確に伝えることも意識しました。
成功事例から学んだ教訓
このプロジェクトを通して、コンテンツマーケティングは単なるキーワードの羅列ではなく、ユーザーのニーズに応える情報提供であることを改めて痛感しました。また、SEO対策はあくまで手段であり、最も重要なのは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供することだと学びました。
コンテンツ不足で悩んでいるあなた!一歩ずつ改善していけば、必ず成果は出ますよ!
SEO対策との連携
SEO対策とコンテンツマーケティングは、車の両輪のような関係です。いくら質の高いコンテンツを制作しても、SEO対策が疎かになっていては、誰にも見てもらえません。逆に、SEO対策だけを重視してコンテンツの質を無視すると、ユーザーはすぐに離れてしまいます。
コンテンツ不足を解決するためには、SEO対策とコンテンツマーケティングをバランス良く連携させることが不可欠です。
SEO視点でのコンテンツ最適化
SEO対策を行う上で重要なのは、キーワードの選定、コンテンツの構造化、内部リンクの最適化など、様々な要素があります。これらの要素を意識することで、検索エンジンからの評価を高め、ウェブサイトへのアクセス数を増やすことができます。
キーワード選定の重要性
まず、キーワード選定は非常に重要です。ユーザーがどのようなキーワードで検索しているのかを把握し、それらのキーワードをコンテンツに適切に盛り込む必要があります。キーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールを活用して、関連性の高いキーワードをリストアップしましょう。
構造化マークアップの活用
構造化マークアップは、検索エンジンにコンテンツの内容を正確に伝えるために有効な手段です。構造化マークアップを施すことで、検索結果にリッチスニペットが表示され、クリック率の向上に繋がる可能性があります。
コンテンツマーケティング視点でのSEO対策
一方、コンテンツマーケティングの視点からは、ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供することが最も重要です。質の高いコンテンツは、ユーザーのエンゲージメントを高め、ウェブサイトの滞在時間を長くする効果があります。
ユーザーのニーズに応えるコンテンツ制作
ユーザーのニーズに応えるためには、ペルソナを設定し、ターゲット層が求める情報を把握する必要があります。アンケート調査やアクセス解析などを通して、ユーザーの疑問や悩みを明確にしましょう。
質の高いコンテンツの重要性
質の高いコンテンツは、ユーザーの満足度を高め、ウェブサイトの信頼性を向上させる効果があります。オリジナルの情報を提供したり、専門的な知識を分かりやすく解説したりすることで、ユーザーを引きつけ、リピーターを増やすことができます。
SEO対策とコンテンツマーケティング、どちらも疎かにしないでくださいね!
ワンポイント
最近マジでコンテンツ不足を感じてるんだよねー。YouTubeもTikTokも、おすすめがマンネリ化してきて、結局同じような動画ばっかり見ちゃうループ。
でさ、真剣に考えたんだけど、コンテンツ不足って、結局「新しい視点」が足りないんじゃないかって思うんだ。
既存のフォーマットに囚われすぎてる気がする。例えば、料理動画だったら、ひたすらレシピ紹介じゃなくて、バックグラウンドにある文化とか、食材のルーツとか、もっと深掘りした方が面白いんじゃないかな?
あとは、視聴者参加型をもっと増やしてもいいかも。ただコメント拾うだけじゃなくて、視聴者からのお題で動画作ったり、コラボ企画とか、インタラクティブな仕掛けがあったら飽きないと思うんだよね。
結局のところ、AIに頼りっきりじゃなくて、人間の創造性をもっと活かす必要があるってことかな。AIはあくまでツールとして、人間のアイデアを具現化する手助けをしてくれる存在だよね。
私も何か面白いこと始めたいなー。まずは、自分が面白いと思えることを発信してみるのが大事かなって思ってる。